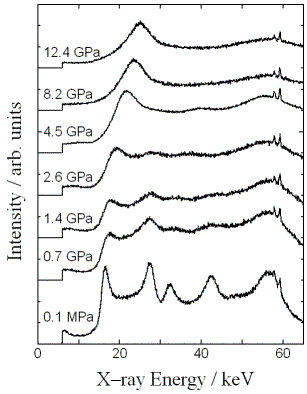
◆ 大型プレスで加圧
フラーレンポリマーでも活躍したMAX80で片浦先生のナノチューブを高温高圧処理しようというものです。
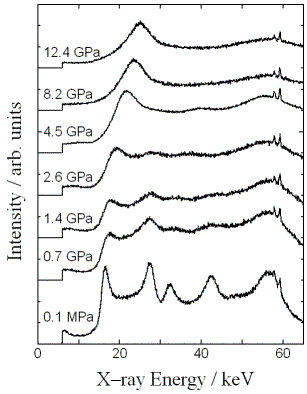
最初は見えなかった
MAX80でエネルギー分散法でとったXRDです。今ではルーチン的にこのくらいのスペクトルが得られますが、最初の実験のときは大変でした。セルを仕掛けてさあとるぞとスイッチをいれるのですがいっこうに回折図形があらわれない。あせります。実験室では汎用のディフラクトメーターで簡単にとれるのにどうして?あまりに慌てて、配向性のせいか(片浦先生の試料はバッキーペーパーの形になっているのでチューブがペーパー面上に配向していると考えられる)と考え、結晶性は落ちるがランダム配向していると考えられる○社のSWNTを長野から東京まで学生に急遽運んでもらい、東京駅で試料をうけとってすぐ、つくばね号でKEKに運んで測定したりしました。そんなことでマシンタイムを2日ほどムダにした後徹夜番の学生2人(松岡、山田)が2時間ほど居眠りするというアクシデントがありました。そしてかれらが目覚めるとそこには欲しかったSWNTのパターンが見えたのです。なんということでしょう。放射光をもってしても低結晶のSWNTは時間を必要としていたのです。数分待ってだめだと判断していたのが原因だったとは。
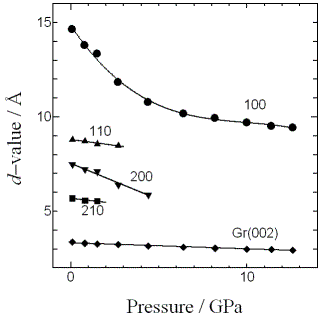
よー縮むぞ!
ともかくパターンがとれるとわかったのでどんどん押します。SWNTの高圧の実験はそれまでにいくつか行われていました。DAC+Ramanがもっとも多く、XRDはTang ら[1], [2]のものと Sharma ら[3]のものがありました。その他の実験も含めてこの時期までの結果はLoa のレビュー[4]に大変良くまとめられています。XRDのほうはTangのほうは回折図形そのものが論文に掲載されてなく、Sharmaのはこれが回折線?というような貧弱な(100)がかすかに見える程度のものでした。片浦チューブ+Max80は複数の回折線を捉えており、情報量の点で完全に上回ったと確信しました。加圧していったときの回折位置の変化を追うと明らかに異方的な収縮が起こっていることが判明しました。また、これまでの報告より、ずっと回折線のシフトが大きいこともすぐわかりました。
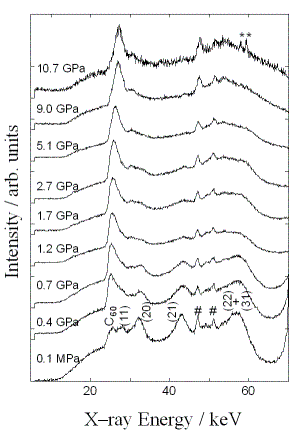
ピーポッドも押したれ
ピーポッドを押すと、上の図のようになりました。ナノチューブ内部に入っているC60が一次元的に配列していることによる回折線の強度が加圧により大きくなったのです。本当かな、と半信半疑ですが、ルーズにパックされていたのが加圧されきれいに整列したのかもしれないと考えています。
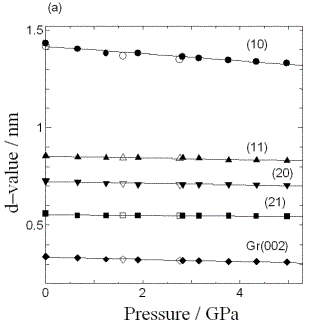
圧媒体とチューブ端
上の実験を終え、ひとつ気がかりなことが残りました。回折線のシフト量がこれまでの報告値と大きく異なるのです。実験自体には自信を持っていましたが、なにが違うのか、が気がかりでした。報告はいずれもDACでした。DACでは一軸押しを避けるため、液体の圧媒体を使用します。一方、MAX80は六方押しですので、圧媒体なしで準静水圧が得られます。圧媒体が何らかの影響を及ぼしていると考えました。チューブ内部に入るのではないか?、そしたら、チューブ端の構造の違いで結果が異なるのではないか?、と考えました。ナノチューブのチューブ端は加熱処理で開けたり閉じたりできます。開端と閉端のナノチューブを用意した上で、MAX80の試料室にテフロンカプセルを入れメタノール、エタノールの混合液を圧媒体とする実験を行いました。上の図はこうやって調べた(端が開いた)ナノチューブの回折線のシフトである。圧媒体を用いないときに比べ、収縮の度合いが小さくなっていることおよび収縮が等方的に起こっていることがわかります。
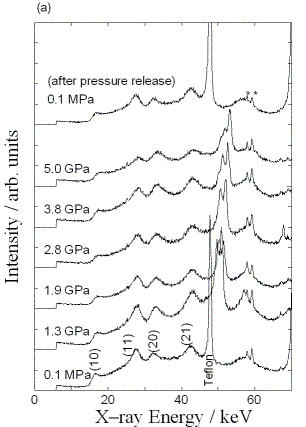
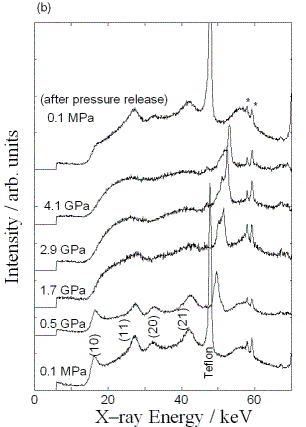
圧媒体とチューブ端(その2)
圧媒体を用いたときは、チューブ端が効いてくるという結果です。(a)は開端、(b)は閉端です。閉端のほうは結晶が持たなくなるようです。